|
←↑→ 前章までにみたように,日本は世界各国と比較しても大量の窒素・リンを農産物の形で輸入している.肥料や漁獲を含めるとさらにその2倍以上が自然環境中に放出されている.本章では,そうした人間活動に由来する窒素・リンのインプットが,日本の自然環境中のフローと比較してどの程度の規模であり,どのような影響をもたらすことが考えられるのかについてみてみることにする. 6-1 日本の自然環境中のフロー 人間活動による窒素・リン負荷との比較のためには,まず日本の自然環境中でどの程度の窒素およびリンが動いているのか,その絶対量を把握することが必要である.しかし,3-2でも述べたように自然環境中の元素フローを正確に求めることは非常に困難であり,それは日本というある程度限定された地域についても同様である.しかし,現在までの研究成果として得られる,大気降下物の通年観測データや河川の窒素・リン濃度データなどを用いて,ある程度の推定を行うことは可能である. 人間以外の理由によるインプット・アウトプットとしては,以下のようなものが考えられる. <インプット> 窒素:大気降下物(降水および乾性降下物)・窒素固定 リン:大気降下物(降水および乾性降下物) <アウトプット> 窒素:脱窒・アンモニアの気化・河川による海洋への流出(有機態・無機態/溶存態・懸濁態) リン:河川による海洋への流出(有機態・無機態/溶存態・懸濁態) インプットについては,多くの研究成果が存在し,その推定値にも比較的信頼性があると考えられるが,アウトプットの項目については,その大きさを推定する上で以下のような問題点が存在する. ・脱窒は,主要発生物である窒素ガス(N2)が大気の主成分であるため,発生量を測定するためには窒素ガスをヘリウムガスなどで置換して実験を行う必要がある.しかし,その場合でも大気からの窒素ガスの混入を避けるのは困難となる.また,副生成物として発生する亜酸化窒素(N2O)と窒素ガスとの比から脱窒量を推定する方法もあるが,温度や酸化還元状態・土壌有機物含量などによって比が大きく変化するため,平均的な脱窒量を求めることは困難となる(西尾, 1994). ・アンモニアの気化による大気への窒素放出量は,脱窒と同様,土壌の有機物含量や水分,酸化還元電位によって大きく変化し,地域的な変化を相殺した妥当な平均値を求めることが困難である(西尾, 1994). ・河川による海洋への流出量を知るためには,自然状態における河川水中の窒素・リン濃度を測定することが必要となる.この手がかりとして,日本全国にわたり広範囲で河川水質を調査した研究(小林, 1971)がある.この研究は,昭和20-30年前後の日本において全国の河川水中の各種成分濃度を測定した先駆的研究である.しかし,測定対象が溶存態の無機イオンに限られており,有機態や懸濁態として存在する窒素・リンの量は含まれていない.一方,現在では有機態・懸濁態の窒素・リンを含めた多くの濃度データが得られているが,すでに多くの河川が人間活動による影響を強く受けており,自然状態での窒素・リンの流出量を全国の平均値として求めることは困難である. 以上のような理由から,アウトプットの各項目の量は大きな誤差を含む値としてしか求めることはできない.このため,地球規模での循環量の計算においても陸地から他のプールへの窒素・リンのフローについては,各プールの値は時間的に変化しない(定常状態)として,インプットとの差し引きから求められることが多い.したがって,本研究ではアウトプットに関するレビューは行わず,インプットの項目を取り上げて人間活動と比較することにした.なお面積などの統計値については,特に断わりのない限り二宮(1996)によった. 大気降下物 大気降下物中の窒素・リンは次の形態で存在する. ・溶存態−有機態/無機態− ・粒子態(可溶性)−有機態/無機態− ・粒子態(不溶性)−有機態/無機態− 溶存態として降下する窒素・リンはそのままで生物に吸収される.また,粒子として降下したもののうち可溶性の部分も水中に溶出し,生物が吸収できる形となる.しかし,不溶性部分ははほぼ全量が溶出することなく沈積し,生物活動を含めた循環に入ることはない.大気降下物の研究はそれが生物活動に与える影響を評価することを目的としており,一般の大気降下物分析においては,溶存態および可溶性の粒子態として抽出される画分(有機・無機の合計)を測定し,全窒素(TN)および全リン(TP)としている(安部, 1989).一方人間活動によるインプットも,易分解性の有機物(輸入農産物・漁獲)あるいは可溶性の無機塩(肥料)として環境中に放出されていると考えられる.したがって本研究においても,人間活動との比較の対象として,不溶性画分を除いた大気降下物を実質的なインプットと考えることにする. 大気降下物として分析値を報告しているものであっても,降水のみのデータで乾性降下物を含んでいない場合や,無機態のみのデータで有機態の降下物を含んでいない場合が多い(田淵・高村, 1985や堤, 1987など).このなかで,安部(1989)による大気降下物のレビューは,乾性降下物や有機態降下物を含んだデータを多く取り扱っている点で本研究にとって有用である.付加的なデータを含め,以下にそのデータを見てみる. <年変動> 降下量の年変動の1つの例として,筑波研究学園都市において降水と乾性降下物を合わせた全大気降下物について測定した結果を図6-1に挙げる.なお,この分析では窒素については無機窒素のみについての分析(TIN: Total Inorganic Nitrogen)となっている.窒素・リンどちらについても,年あたりの降下量は大きく変化するものの,平均すれば窒素は11kg/ha,リンは0.35kg/ha付近を中心に変動していることが分かる. 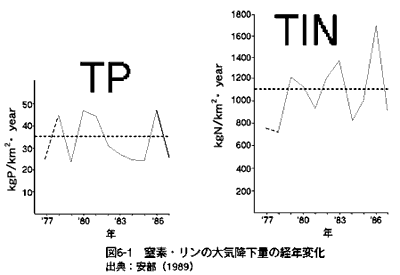 <地域変動> つぎに,日本各地における測定値を見てみる(表6-1).これらの測定の多くは散発的であって,地域的特性の把握という点から見ると必ずしも十分ではない.表6-1を見ても分かるように,日本各地における全窒素・全リンの降下量は測定地点によって大きく異なる.しかし,これらの違いを無視してその頻度分布を見ると,図6-2のように比較的限られた範囲の値をとることが認められる .これらの分布の中央値は,全窒素については約12kg/ha,全リンについては約0.45kg/haと考えられる. 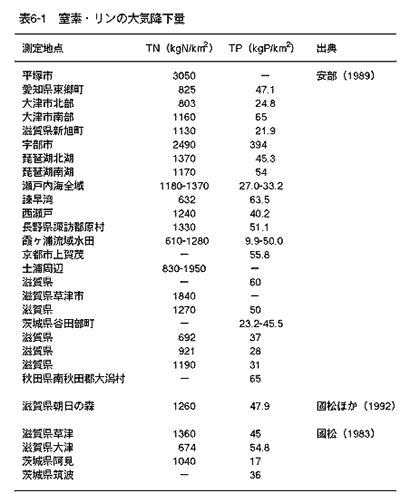 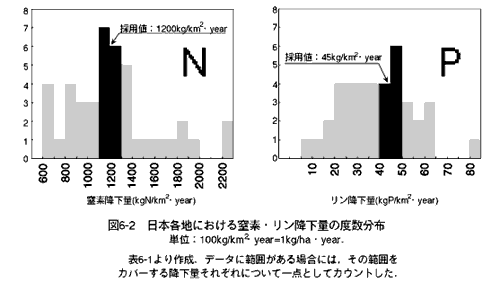 以上のような変動を考慮し,日本全体の面積あたり平均降下量として,窒素12kg/ha,リン0.45kg/haを採用することにした.この値に日本の国土面積37,800,000haをかけると,窒素4.5×1011g,リン1.7×1010gとなる. 窒素固定 陸地へのインプットを考えた場合,リンについては大気降下物のみとなるが,窒素については窒素固定菌による空気中窒素の生物学的固定が存在する.以下にそれぞれの生態系における窒素固定量を求めてみる. <森林> 窒素固定を行う微生物は共生と非共生に大別できる.共生のものはマメ科植物の他ハンノキ属などに根粒を作り,これらの窒素固定能は高い(100-300kg/ha).これらの樹種は窒素に欠乏した土壌でも生育できるため,先駆種が多く,山火事の直後といった遷移の初期に窒素を急速に集積する.しかし,成熟した森林で,すでに土壌に有機物や窒素の集積が進んでいる場合には,非共生の窒素固定菌が重要となる. 非共生の窒素固定菌による窒素固定の速度は年間で数kg/haから20-30kg/haの範囲にあり,温帯林では年間1-20kg/haである.タイガの生産力の高い落葉樹林で年間17kg/ha,温帯の落葉樹林で14kg/haと報告されている(堤, 1987).以上の値より日本の森林における窒素固定量の仮の平均値として年間16kg/haを採用する.この値を用いると,日本の森林面積は25,100,000ha(1993年)であるから,森林における窒素固定は4.0×1011g/yearとなる. <水田> 水田では水中に生育するラン藻類によって窒素固定が行われる.水田の窒素固定量についてはBurns and Hardy(1975)にまとめられたものがあり,10-55kg/haの範囲にあるとされている.また,國松(1983)によれば日本の平均的な水田における窒素固定量は年間約47kg/haとされている.以上の報告から,日本の水田における窒素固定量を50kg/haとした.日本の水田面積は2,782,000ha(1993)であるから,水田における窒素固定量は1.4×1011g/yearと計算できる. <畑地> 畑地の窒素固定能は栽培している作物によって大きく異なり,マメ科作物の生産農地では年間で平均79kg/haの窒素を固定するが,通常の作物の場合は47kg/ha程度であると考えることができる(國松, 1983). 日本の畑地面積は,1993年度の統計で2,343,000haであり,マメ科作物の植えつけ面積173,569ha(ダイズ,アズキ,ラッカセイ,インゲン,エンドウ,ソラマメの合計;農林水産省, 1995より)である.したがって,マメ科作物を植えつけた畑地の窒素固定量を79kg/ha,その他を47kg/haとすると,畑地全体の窒素固定量は8.8×1010g/yearとなる. <牧草地> 牧草地の窒素固定能については,200kg/ha(國松, 1983)を採用した.日本の牧草地面積660,700ha(1993)より日本の牧草地における窒素固定量は1.3×1011g/yearと計算できる. <果樹園> 果樹園の窒素固定能については森林と同じ(16kg/ha)と考え,果樹園の面積439,100ha(1993)をかけて,7.0×109g/yearと計算できる. <その他> 農耕地と森林以外に分類される土地(6,500,000ha)は,宅地や道路のほか,荒れ地,草原,湿地などが考えられる.これらの土地については,Burns and Hardy(1975)における草地(permanent meadows, grasslands)と同程度の窒素固定能と考え,15kg/haを採用した.これより,窒素固定量は9.8×1010g/yearとなる. 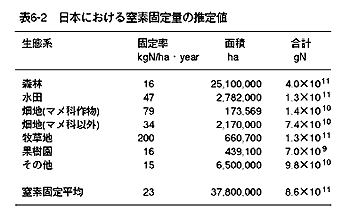 以上の結果をまとめたのが表6-2である.合計すると,日本全体で生物による窒素固定量は8.6×1011g/yearとなる. 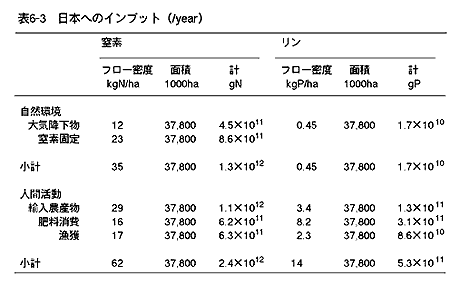 3章で述べた文献値によれば,陸地への窒素・リンのインプットはそれぞれ2.6-4.2×1014gN/year,3.2-9.2×1012gP/yearであった.これを世界の陸地面積134億ha(F.A.O., 1994)で割ると,単位面積あたりのフローは窒素・リンそれぞれについて年あたり19-31kgN/ha,0.24-0.69kgP/haとなる. 本章で計算した日本での平均のインプットは,表6-3より,窒素・リンそれぞれ35kgN/ha,0.45kgP/haである.この値は,文献値から得られる世界全体の平均的なフローに比べてもほぼ妥当な値と考えられる. 6-2 自然環境中のフローと人間活動によるフローの比較 人間活動による日本へのインプットを考える.具体的な数値については4章で計算した数値を用いることにする. まず窒素については,肥料消費が6.2×1011g/year,輸入農産物中の窒素が1.1×1012g/year,漁獲による負荷が6.3×1011g/yearである.この小計は2.4×1012g/yearとなる.この値を自然環境中のフローと比較すると,農産物の輸入だけでほぼ自然界でのインプットの量に匹敵し,肥料消費や漁獲を含めるとその2倍程度となっている. つぎに,リンについてみると,肥料消費が3.1×1011g/year,輸入農産物中のリンが1.3×1011g/year,漁獲による負荷が8.6×1010g/yearである.この小計は5.3×1011g/yearとなる.一方,大気降下物によるインプットは1.7×1010gであり,圧倒的(30倍以上)に人間活動の規模が上回っている. 河川による無機態窒素およびリンの海洋への流出量 6-1にも述べたように,河川水中の窒素・リンには無機溶存態以外にも,有機態,懸濁態,粒子態などの形態があり,日本において自然状態にある河川水の全窒素・全リンの濃度を求めたデータは得られなかった.しかし,人間活動によって河川に流入する窒素・リンの一部も,分解・溶出して無機溶存態となる.一つの目安とするために,自然状態で無機態として河川を経て海洋へと流出する窒素・リンの量を計算してみよう. 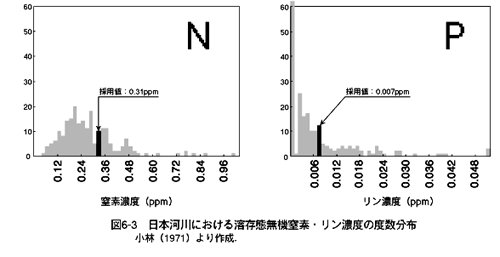 小林(1971)によれば,昭和20-30年前後の日本において全国500河川の平均濃度(流量加算)は無機窒素(硝酸態とアンモニア態)で0.31ppm,無機リン(リン酸イオン)で0.007ppmである(図6-3).日本の平均降水量を1800mm,降水の蒸発率を4割(國松, 1995)とすると,日本の国土面積(3.78×105km2)より河川水の供給量は年あたり3.4×1017gとなる.さらに,窒素については河川水中の有機態窒素の量は無機態窒素と同程度であるとされている(Soderlund and Svensson, 1976).また,リンについては河川水中に微粒子(Particle)として存在する量は,溶存態リンの10倍程度とされている(Jahnke, 1992).したがって,合計の窒素.リン濃度としてはそれぞれ0.62ppm,0.077ppm程度と考えることができ,自然状態の河川によって海洋に運ばれる窒素,リンの量は年間2.1×108g,2.6×107gと計算される(表6-4). 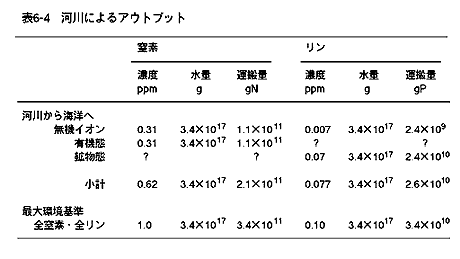 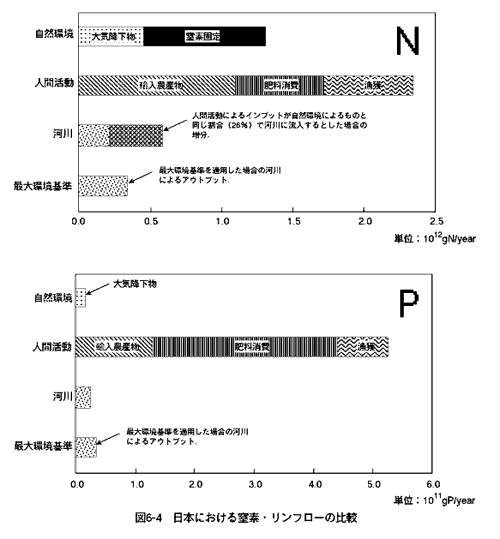 この結果の妥当性であるが,窒素については26%が河川水に入るという仮定は,畑地における土壌中窒素の溶脱率22.2%(小川, 1995)と比較しても適当と考えられる.しかし,リンについては土壌の固定能が非常に高いために全量が溶出するとは考えにくい.人間活動に由来するリンがどの程度の割合で河川水中に流入するかについては,今後の研究課題である.しかし,現在でも湖沼の富栄養化は深刻な問題となっており(表6-5),これまでに見た人間活動由来のインプットの総量を減らすことが必要であると思われる. 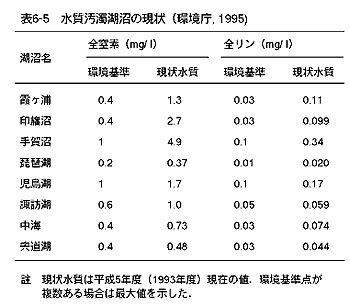 6-3 人間活動が自然環境に与える影響について 農産物貿易を含めた人間活動が,日本の自然環境にどの程度の影響を与えるかについては,日本全体を平均した自然環境中のフローと比較するだけでは把握できない.というのは,人間活動は人口や物資の都市域への集中をはじめ地域的に大きな偏りが存在するためである.河川水・地下水中へ流入する窒素・リンという点では,人間活動が自然環境に及ぼす影響は局地的な問題と考えられる. そこでつぎに,実際の輸入農産物が日本国内のどこに集中しているかについてみてみることにする. 輸入農産物中の窒素・リンのゆくえ 日本の輸入農産物中の窒素およびリンはそれぞれ1.1×1012g/year,1.3×1011g/yearと莫大な量であるが,それらの物資はどのような性質のもので日本のどこに集中しているのであろうか. 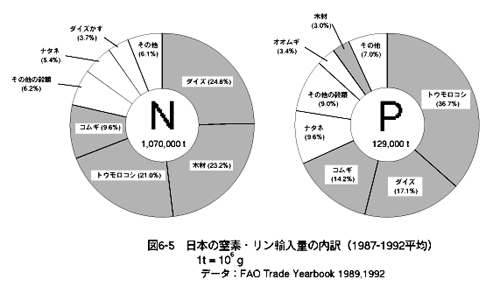 輸入農産物による環境汚染−北海道酪農地帯での研究− 酪農は農場内の牧草を飼料として利用する傾向があるが,日本では飼育頭数の増加にともない家畜飼料の半分近くを購入飼料すなわち輸入飼料に頼るようになっている.したがって,輸入農産物(飼料穀物)由来の過剰窒素が周辺環境を汚染している可能性がある.大村(1995)は北海道の酪農と水質についての研究を行っており,家畜糞尿が周辺地域の自然環境に与える影響について以下のように述べている. ・発生源別にみると酪農地帯で発生する負荷は,畜舎や堆肥置き場を中心とした点汚染源と,農地からの肥料成分の流出による面汚染源に分けられる.また流出形態別にみると,おもに融雪時に発生する表面流出と,夏の後半から秋の長雨の時期に多く発生する浸透流出に分けられる. ・点汚染源の実例として,融雪時に堆肥置き場を経由した表面流去水を対象に調査したところ,窒素:597ppm,リン:64ppmという極めて高い濃度が検出された.ただし,このような高濃度の栄養塩を含む流去水がそのまま河川に流れ込むわけではなく,表面流去水の成分濃度は懸濁態成分を中心に流出過程で低減する.低減率は流下距離とともに傾斜の緩急や植生の有無によって変化する.実際に比較試験をおこなった結果,起点で窒素:125ppm,リン:10.6ppmであった流去水が,河川流入地点において,裸地(畑地)条件では窒素・リンともに9ppm,草地条件では窒素:4ppm,リンについては測定濃度以下と減少した. ・また,浸透流出水については,糞および尿について50kg/m2を施用(仮比重を1として5cmの厚さに相当)した場合の流出水の濃度を測定したところ,リンは測定限度以下となったが,窒素については糞で平均24ppm,尿で平均162ppmとかなり高い値となった. リンについては土壌に浸透させた場合には固定されて流出しないためにあまり影響はないと考えられる.しかし,窒素は陰イオンである硝酸態窒素となり,土壌中に固定されずに流出する.昭和20-30年当時の日本における河川水の無機イオン平均濃度は窒素:0.31ppm,リン:0.007ppm(小林, 1971)である.また,環境庁の環境基準によれば湖沼水の最大許容濃度は窒素:1ppm,リン:0.1ppmである.これらの値と比較すると,畜産廃棄物からの流出水が非常に高濃度の窒素を含んでいることが分かる.したがって,糞尿処理施設の不備による流出水は,周辺水域の水質に無視できない影響を与える可能性が存在する.また,酪農地帯は自然環境が厳しく農業生産性もあまり上がらない(すなわち牧草しか生えない)地域に位置することが多い.そのような地域は,高原牧場など河川の上流域,中山間地帯に多く分布する.したがって,家畜糞尿由来の窒素を高濃度に含んだ河川水が下流域全体の水質を変化させ,水田の潅漑水中の窒素濃度が上昇することも予想される.高濃度の窒素を含む潅漑水(3ppm以上)の施用は水稲の生産性に悪影響を与えることが指摘されており(國松, 1995),現実に被害を生じている可能性も高い.水稲の潅漑水量は平均一作10aあたり1500t程度といわれている(長谷川ほか, 1979).その中に窒素が1ppm含まれているとすると,窒素の総量は1.5kgにのぼることになる.水田への窒素の標準施肥量は一作10a当たり10kgと畑地に比べて少ないため,数ppmの窒素が潅漑水に含まれている場合標準レベルの施肥を行った場合には,過剰の窒素により水稲に濃度障害がでる危険性がある. 現在北海道で飼育されている牛は,乳牛と肉牛を会わせると100万頭(全国では約500万頭)をこえており,乳牛の国内シェアは45%を占めている.酪農経営にともなう糞尿由来の負荷は,概算で窒素6.6万トンおよびリン1.1万トン(1万トン=1010g)に達している(大村, 1995).北海道で排出される家畜の糞尿だけで日本の輸入農産物によるインプットの6-10%にあたる.道内の多くの酪農家では経営規模の拡大に対して糞尿処理施設の整備が遅れており,酪農関連排水による悪臭や水質汚濁などの環境問題を引き起こしている(水間, 1991).このような影響は北海道に限られることではなく,他の畜産地帯(鹿児島・宮崎・熊本といった九州の肉牛生産地域など)でも十分起こりうる.平成元年(1989年)現在のデータより計算すると,家畜全体から発生する糞尿の量は人間にして1億8000人分に達し(水間, 1991),人間の原単位である,窒素:9.0×100g,リン(P2O5):9.0×10-1g(富岡, 1993)を採用すると,窒素にして5.9×1011g/year,リンにして2.6×1010g/yearとなる.これを自然界のフロー(表6-3, 4,図6-4)と比べてみても膨大な量に達していることが分かる. ←↑→ [ Reference ] 安部喜也, 大気降下物による汚濁負荷, 『河川汚濁のモデル解析』, 國松孝男・村岡浩爾編著, 技報堂出版, 1989, pp. 24-34 Burns, R. C. and Hardy, R. W. F., Nitrogen Fixation in Bacteria and Higher Plants, Springer−Verlag, 1975, pp. 39-60 F.A.O., FAO Yearbook Production 1992, 1994 長谷川浩・竹内史郎・奥村俊勝, 長期無施肥田における水稲諸形質の位置的変動, 『近畿大学農学部紀要』, 第12号, 1979, pp. 109-115 北海道土壌肥料懇話会編, 『北海道土壌肥料研究通信 第42回シンポジウムと特集 物質循環からみた環境保全』, 北海道土壌肥料懇話会, 1996 Jahnke, R. A., 1992, "The Phosphorus Cycle", Global Biogeochemical Cycles, Academic Press, pp. 301-315 環境庁, 『環境白書(各論)−平成7年度版−』, 大蔵省印刷局, 1995, pp. 156-157 小林純, 『水の健康診断』, 岩波新書, 付録, pp. 1-17, 1971 國松孝男, 『汚水の農地への還元利用 −その理論と実例−』, 農業土木学会畑地潅漑研究部会編, 畑地農業振興会, 1983, pp. 31-62 國松孝男・須戸幹・島田佳津比古・海老沢秀夫, 朽木『朝日の森』落葉広葉樹二次林における水質形成機構に関する研究(I)−隣接する2試験流域から流出する渓流水の水質特性の比較−, 『森林文化研究』, vol. 13, no.1, 1992, pp.81-94 國松孝男, 水資源と水環境, 『農業と環境』, 久馬一剛・祖田修編著, 富民協会, 1995, pp. 73-147 久馬一剛・庄子貞雄・鍬塚昭三・服部勉・和田光史・加藤芳朗・和田秀樹・大羽裕・岡島秀夫・高井康雄, 『新土壌学』, 朝倉書店, 1984, p. 104 三輪睿太郎・小川吉雄, 集中する窒素をわが国の土は消化できるか, 『科学』, vol. 58, no. 10, 1988a, pp. 631-638 三輪睿太郎, 外来窒素とわが国農地の受容力, 『化学と生物』, vol. 26, 1988b, pp. 465-469 水間豊, 『畜産の近未来−国際化時代の新畜産ハンドブック−』, 川島書店, 1991, pp. 17-20 二宮道明編, 『データブック オブ ザ ワールド 1996年版』, 二宮書店, 1996 西尾隆, 耕地土壌の脱窒過程, 『日本土壌肥料学雑誌』, 第65巻, 第4号, 1994, pp. 463-471 農林水産省, 『ポケット農林水産統計』, 大蔵省出版局, 平成7年度版, 1995 小川忠四郎, 『生物地球化学−環境化学への基礎と応用−』, 東海大学出版会, pp. 17-21, 1980 小川吉雄, 農地における窒素循環の再生−畑作地域における地下水汚染と農法転換の可能性−, 『北海道土壌肥料研究通信 第42回シンポジウムと特集 物質循環からみた環境保全』, 北海道土壌肥料懇話会編, pp. 93-102, 1995 大村邦男, 家畜糞尿の活用と酪農地帯の環境保全, 『北海道土壌肥料研究通信 第42回シンポジウムと特集 物質循環からみた環境保全』, 北海道土壌肥料懇話会編, pp. 17-24, 1995 Soderlund, R and Svensson, B. H., "The Global Nitrogen Cycle", Nitrogen, Phosphorus and Sulphur−Global Cycles., SCOPE Report 7., Ecological Bulletins, vol.22, 1976, pp. 23-73 田淵俊雄・高村義親, 『集水域からの窒素・リンの流出』, 東京大学出版会, 1985, pp. 18-37 田淵俊雄, 集水域の土地利用・畜産と窒素流出, 『北海道土壌肥料研究通信 第42回シンポジウムと特集 物質循環からみた環境保全』, 北海道土壌肥料懇話会編, pp. 81-92, 1995 Taylor, S.R., "Abundance of chemical elements in the continental crust: A new table", Geochimica et Cosmochimica Acta, vol. 28, 1964, pp. 1273-1285 富岡昌雄, 『資源循環農業論−「リサイクリングの経済学」の試み−』, 近代文藝社, 1993, p.83 堤利夫, 『森林の物質循環』, UPバイオロジー67, 東京大学出版会, 1987, pp. 49-51 |